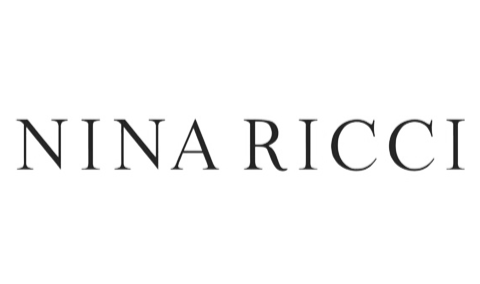メガネの国家検定資格
眼鏡作製技能士
(1級2名、2級1名)在籍
むつ下北地域唯一の
認定補聴器専門店
補聴器のプロ「認定補聴器技能者」
3名在籍

認定補聴器専門店とは
公益財団法人テクノイド協会が補聴器販売店からの認定申請に基づき、店舗の補聴器販売事業が、適正な販売を行う為に導守すべきものとして定めている「認定補聴器専門店業務運営基準」に適合して行われていると認定し、協会の認定補聴器専門店登録簿に登録、認定証書を交付している補聴器販売店です


2022年から「国家検定資格」として制定されました。
眼鏡作製において、お客様の眼鏡の使用状況・使用目的を聞き取ると共に、視力の測定、レンズ・フレームの販売、加工前作業、レンズ発注・加工、フィッティング、引き渡し、アフターケアを行う眼鏡作製の総合エキスパートです。


A1. 補聴器は、厚生労働省の認証を取得した管理医療機器です。薬機法という法律に基づき、性能・安全性が考慮されたつくりになっております。聴力に合わせ音質・音量の調整が出来ます。
集音器は、周りの音を大きくする機能がメインのため、きめ細かい音の調整が出来ません。
A2.補聴器の効果が左右ともに見込める場合、音の方向が分かりやすくなったり、言葉の聞き分け能力の向上により、言葉や聞きやすくなるなど、左右ともに装用する「両耳装用」にはメリットがあります。
A3. 音の調整幅・雑音を抑える力・環境に合わせで自動で調整するなど、補聴器の内部の機能によって値段が違います。 マイクやスピーカーの差というより、音声を分析してどのような音を届けるか「考える」頭脳部分のちがいになります。
A4.補聴器の維持費は電池式補聴器の場合は電池代、充電式補聴器の場合は充電に要する電気代となります。 精密電子機器である補聴器は、落下などの強い衝撃が加えられたり、長い間水分に触れたりすると故障してしまうことがあります。メーカー保証期間内であれば、自然故障に関しては、無償で修理を行ってもらえる場合もあります。
A5. 店内での試聴体験は無料で行っております。問診でお困りの状況をお伺いしたり、聴力測定などで約1時間かかりますので、事前にご予約いただくとスムーズにご案内出来ます。
職場やご家庭で実際に装着して試せる貸し出しも有償で行っております。
A6.難聴になると、必要な音が聞こえなかったり、危険を察知する能力が低下したり、認知症のリスクが大きくなると報告されています。認知症のリスクに関しては、日本の急速な高齢化を受けて、厚生労働省が2015年、「新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)」を策定し、そのなかで難聴が認知症の危険因子とされています。難聴は、単に「音が聞こえにくい」だけの問題ではありません。会話が億劫になって人との関わりが減ると、外出の機会も少なくなりがちです。
その結果、脳への刺激が減り、認知機能の低下につながることもあります。
A7. 聴力測定結果にそった調整で正しい使い方をしていれば補聴器が原因で聴力が低下する事はありません。
しかしながら補聴器の装用を開始してから様々な要因(加齢等)から、聴力低下が進行した場合は聴力に合わせて調整します。強すぎる音でなく、言葉を理解できるようにする音を目指して調整していきます。不用意に大きい音で聴力が低下することがないように設定しております。
A8. 補聴器は汗、湿気、ホコリ等の原因により、故障につながることが多くありますので、購入した販売店で定期的に点検メンテナンスを受けることをおすすめします。
補聴器の定期的メンテナンスは、使用頻度や使用環境によって違いますが、3ヶ月に1度程度をおすすめしております。ご本人様がご来店できない場合は、ご家族のかたに「補聴器だけ」当店にお届けいただければ20分ほどでメンテナンスいたしております。
A9. 必ず外してください。超音波療法(理学療法)、レントゲン撮影、MRスキャン(MRI)、CTスキャンなどの放射線治療や撮影を受ける場合は、必ず事前に補聴器を取り外してください。
A10. 補聴器は、使う人の聴力や聞こえの状態に合わせて、機種の選択やフィッティングを行うため、たとえ同じ機種の補聴器であっても、使う人が違えば中身は全く別物になります。そのため、他人の補聴器を使うことは出来ません。
A11.
可能です。補聴器のマイクが聞きやすい位置があります。そこに合わせるようにします。
(近年の補聴器の場合Bluetooth通信規格を使い、直接スマホから補聴器に音声を伝えることが可能です。両耳装用の場合は左右の耳で聞こえるのでさらによく聴こえます。)
補聴器を付けて携帯電話や電話を使う場合、受話器を耳にぴったりとつけると、ハウリングと呼ばれる「ピーピー音」が鳴ることがあります。
耳かけ型の場合、受話器の耳の上にずらし補聴器のマイク(補聴器の上部のあな)と受話器の中心が同じ高さになるようにしてください。
耳あな型の場合は、受話器で補聴器を覆い被さないよう注意し、受話器の持つ手の甲を自分の身体の前方に少しひねり、受話器と補聴器の間に少し隙間ができるようにして耳にあてて下さい。

お電話
TEL 0175-22-2932
予約フォーム
当店からのご返信が翌日以降になる場合がございます。お急ぎの場合はお電話くださいませ
お電話
TEL 0175-22-2932
予約フォーム
当店からのご返信が翌日以降になる場合がございます。お急ぎの場合はお電話くださいませ
補聴器試聴体験やご相談など、こちらのご予約フォームより承っております。


News ~お知らせ~
News
| ・2025年10月10日 秋の大感謝祭 10月31日まで |
|---|
| 2025年03月16日 お知らせ 補聴器の価格 を更新しました |
| ・2024年12月29日 お知らせ 年末年始の営業時間 のお知らせ |
| ・2024年12月09日 お知らせ 単焦点・多焦点レンズ価格 を更新しました。 |
Brands ~取扱いメガネ~
Brands
BRAND LIST お取扱いブランドリスト一覧
Guide
Guide ~店舗情報~


所在地:青森県むつ市小川町2-4-14
マエダ本店様の通り、エネオス テンダーランドむつSS様の向かい側
営業時間:10:00 ~ 19:00
定休日:定休日なし(年末年始定休日あり)
TEL:0175-22-2932
FAX:0175-22-0319